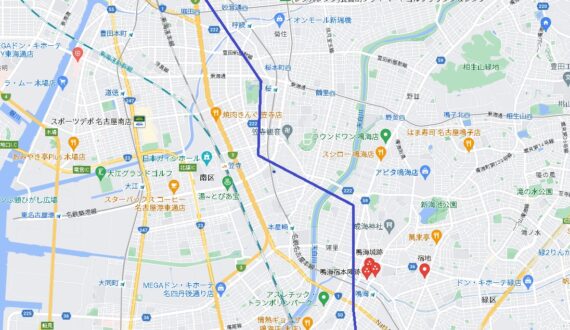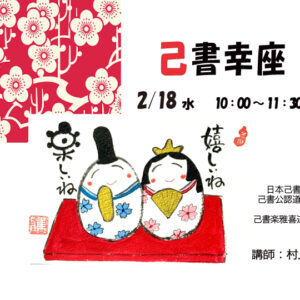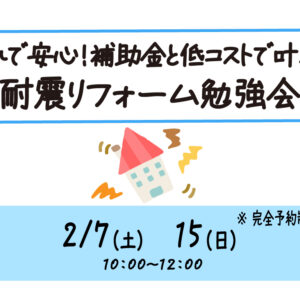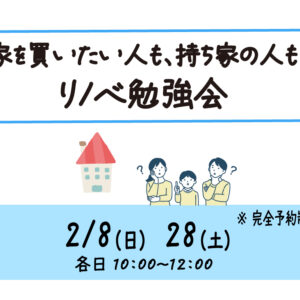ジャズの世界ではスタンダードが数多く演奏され、今もそれは不変。
例えば「A列車で行こう」なんて曲は延々と受け継がれ、今聴いても古さを感じさせない名曲。
家にもスタンダードがあります。伝統的な和の建築を私はクラシックスタンダードと呼んでいますが・・・

江戸期に入って熟成された日本の建築の基本形がこれです。
絞り丸太、床の間、違い棚などをこしらえたつくりを書院造りと言います。
長押は武家屋敷の標準仕様。長押の裏に長槍を忍ばせ、くせ者が現れた際の戦闘武器を保管する役目。
違い棚の丸みは筆返しと言って筆が落ちないようにするためのもの。
これはネットから拝借した写真ですが、筆が転がらないようにするために湾曲した材をつけています。

上の棚と下の棚をつなぐ柱のようなものは海老束と言います。
和室のパーツには様々なネーミングがあるということを知っていただければ嬉しいな。
築50年近く経過している書院造りはとても大工の技術レベルが高いのがわかります。私の親方世代がやっていたころ。辣腕が多かったですよ。
今の大工と言われる人たちにこれができる人が何%いるでしょうか・・・10人中1人もいないと思うよ。それだけ腕利き大工が減ってしまったということ。
既製品の貼り付け大工ではこういう正統派の仕事は無理。
凛々しさがある正統派の和の空間をもっと見直してほしいなと思います。
日本人という大テーマをもった政権に変わったことだし、家づくりも少しばかり伝統的なものを振り返るのもいいと思うよ。
日本の伝統的なものに家事動線+収納計画+耐震+断熱という最近のトレンドをミックスするとまさにクラシックスタンダードになるのではと思っています。