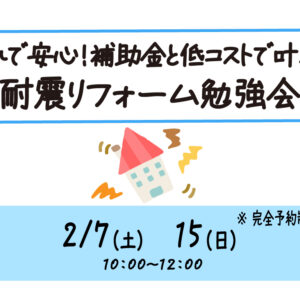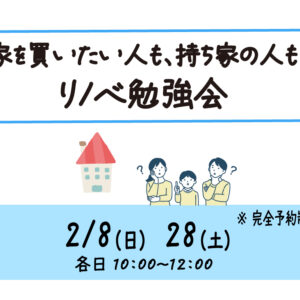外装は変えられていましたが、GoogleMapで見た外部の構えから「おそらく質は良し」と思っていましたが、中に入った瞬間「この家はええな」と感じた一棟。
この感覚は結構鋭いと自画自賛しています、笑。
経験値の高さ故の感覚と思います。大工時代に様々な木造住宅を見てきたし、質の良し悪しは見た瞬間の水平・垂直ラインで感じるんだと思います。下手くそなリフォームされてしまうとそこがわからなくなりますが、そういう時でも小屋裏を見れば一発でわかります。
質の良し悪しはとにかく隠蔽された部分のチェックからですよん。
下の写真、火打梁にメッキがされたボルトが貫通。これは旧耐震(昭和56年まで)から変わった時のものです。おまけに梁が太い。「は七」と書かれた小屋束がありますが、手書き。大工の墨付け、手刻みです。

野地板は桧の幅板。隙間があるけど、これでいいんですよ。垂木は桧1.5寸角。曲げに強い。
奥に斜めに野地板が貼ってありますが、これは外壁のモルタル下地の板。当時は外壁は左官のモルタル塗りかトタン板のどちらかです。ちゃんと奥まで延ばしてあるのがいい。

電気配線も梁にステップルで止め、そこから天井板を貫通している。これが正解。酷いとステップルで止めずにいきなり天井裏を這わせるような電気屋もいる。電線を短くして利ざやを稼ごうとする浅知恵は小賢しい。
寄棟部分の隅木。隅木に垂木が45度で取り付け。この垂木を配付(はいづけ)垂木といいます。
隅木に掘り込みまではしていませんが、ちゃんと3寸釘で取り付けられている。電気配線も美しいでしょ?
梁と梁の緊結にはメッキされた釘打ちではない羽子板ボルトが使用。良いです。梁と小屋束の仕口にはかすがいで緊結。これも定番でオッケー。

梁にあごを作って大きな梁をかけている。この大工、屋根の重さと梁の組み方をわかっている。羽子板ボルトの貫通ボルトも緩みなくオッケー。
土壁が梁の下までしっかりとつけてあるのもグッド。

こう言うのを見ると築39年で古くてダメと言ってはならないのです。
最近は築年数で古いから壊して建て替えした方がいいとかすぐ言う業界。何をほざいているんだよと言いたい。
ちゃんとした理由なくそう言うことを言うのは素人というのです。
実はこの建物は見にいく前に、建物の情報をもらって耐震の精密診断で現況診断をしました。
現行基準の構造評点に少し不足ですが、壁を5、6枚補強するだけで耐震等級1をクリアします。
屋根の土葺き瓦を軽い屋根に変更するだけで耐震等級3に変貌します。
そういう理にかなった構造しているのです。
こういうものを見せてもらうと職人の良心、プライドをリアルに感じて幸せな気持ちになります。
まだまだこういう建物は数多くあり。大切にしてほしいです。「壊した方がいい」とか「古いから危ない」とか言われたら、私にまずは見せて〜。正直なジャッジしますよー★