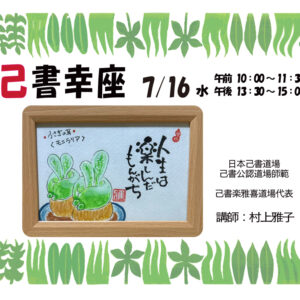会社の南東角に立てる予定の立て看板、少しずつ下地作りしています。
オール現場で使えない材ばかりを加工してステンレス柱に固定。
右端にある杭のような木材は、実際に杭として使っていたものを斜めカットして使っていますぞ。

使えない木材って曲がっていたり、割れていたりして加工や取付面倒なんだよ(笑)

そっくり返っていた垂木もこのように使えば一人前(^^)/

こんな材の使い方していると、大工小僧の時を思い出します。
現場で端材がほとんど出なかった。
親方から「3寸以下のものだけ捨てていい」と言われ、3寸以上のものは全て下地に使ったりと色々と工夫したもの。
3寸=9㎝です。
捨てると言っても、当時は現場のドラム缶で焚火です。私のような職人の見習いが焚き木をして親方に「どうぞ」とやってたよ。今にして思うと凄い時代。親方に教えを乞うのだから、下支えやるのは当たり前だし、授業料寄こせと言われた時代だったもの。焚火をしているのは今ではあり得ないよね。
でも当たり前に火があった時代なので、その良さと怖さは同時に学んでいたと思います。
今回使えなくなった材でをしっかり使ったけど、昔なら当たり前だったんだよ。
「この材料はお客様がお金を払って買ったものだぞ。粗末にするな」と言われたものです。
お客様からも「材料を大切に使ってくれるから嬉しい」と何度も言われたよ。
木材は大工の見習いの賃金より高い時代。そりゃ人より木材が大切となるに決まっている。
今は逆。人が高い。
変わったねぇ。